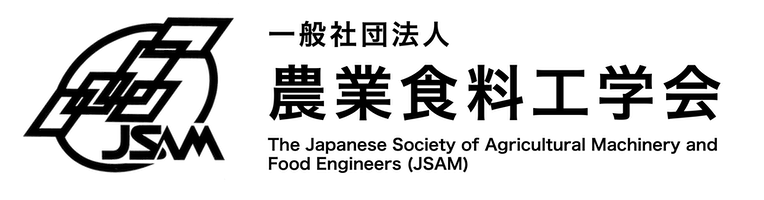会長挨拶

この度,令和5年6月24日開催の定期総会・臨時理事会において会長に選任され,今期(2023年6月~2024年5月)の会長を務めることになりました。会員・産業界・各種団体の皆様方のご支援・ご協力を仰ぎながら微力ではございますが,職務を遂行して参りたいと存じます.
また,本年5月から新型コロナ感染症による行動制限もなくなり,様々な社会活動が活発になり,学会活動も対面形式での会議やシンポジウムが再開できることとなりました。皆様方におかれましても,従前にもまして活発に学会の運営や活動にご参加頂きたいと思います。
本学会は,1937年に設立された「農業機械学会」を母体として,2013年9月に学会名称を「農業食料工学会」に改称しました。その後,2019年4月に任意団体から一般社団法人となって4年が経過し,井上英二前会長の元で新たな会員制度や選挙時期の変更が行われ,法人化への移行後の手続きもほぼ完了しました。そのため,法人化後運営委員会は一旦閉じて,学会運営体制は12の委員会に加え,4つ地域ブロックと4つの部会で進めて行くこととしました。
農業を取り巻く環境としては,世界人口が80億人を突破し,食料の安定した生産と供給が益々重要となっています。また,環境とエネルギーの面からも「2050年脱炭素社会の実現に向けた農林水産分野の取り組み」として,農林水産省から「みどりの食料システム戦略」がまとめられ,本学会にも大いに関わる革新的な技術の研究開発や普及が提言されており,会員・産業界・各種団体の皆様方にとっても,大変な追い風となっています。本学会を学術的な交流の場として,学術研究の成果発信と普及に活用いただきたいと思います。
最後になりましたが,委員会,地域ブロック,部会,事務局,ならびに会員の皆様のご協力・ご支援を賜りながら学会の運営と活動を進めて参りたいと存じますのでよろしくお願い申し上げます。